雑談掲示板
- フルーツペディア6
- 日時: 2025/06/13 05:23
- 名前: 毛筒代 (ID: v/SyGyp.)
フルーツペディア6へ、ようこそ!
フルーツペディア6は、ほぼ小説カキコ(>>741)以外のことを載せた百科事典です。
※予め記事名と内容は決めてありますので、ノートページ(議論など)は「死ぬかと思ったわ」(別掲示板)にて投稿してください。
※記事を閲覧する前に、以下のことをお守りください。
[荒らし行為について]
フルーツペディア6では、記事の作成を妨害するような行為、または規則を破る行為を、荒らし行為と呼んでいます。
荒らし行為をした場合には、緊急ロック(特に記述のないまま、突然ロックすること。期間は内容による)や警告(その人の掲示板にて注意)をさせていただくことがありますので、ご注意ください。
[良質な記事]
良質な記事とは、フルーツペディア6において読みやすいと判断された記事のことを指します。多くの記事が良質な記事になれるよう、出典や脚注などを用いて頑張りましょう。
良質な記事の例については、>>13(梅雨)を参照してください。
[名前の混入について]
毛筒代による、なりすまし行為の為、一部の名前が混入していることがありますが、気にしないでください。
[記事の手助け]
記事を作成するのが初めてな方へ、少しだけヒントを差し上げます。
・基本的なルールを守りましょう
・節を使ってみましょう
・改行を用いて、文を読みやすくしましょう
・出典を追加しましょう
・どうしても定まらない文章には、注釈を追加しましょう
・外部リンクを張ってみましょう
・「・」を付けて分かりやすくしましょう
・記事が、ある程度完成したら一度、読み直してみましょう(もし訂正があったら雑草取りなどを行いましょう)
[見たい記事へジャンプ!]
見たい記事へ自由に飛んでください(番号は振ってありますが順序性はありません)。
>>1雨
>>2家
>>3人
>>4動物
>>5雲
>>6晴れ
>>7曇り
>>8空
>>9雪
>>10雷
>>11台風
>>12地震
>>13梅雨
>>14日本
>>15アメリカ
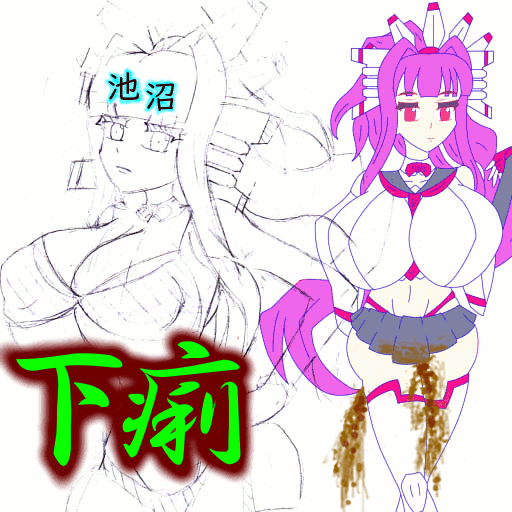
全レスもどる
 雨 ( No.1 )
雨 ( No.1 )- 日時: 2025/06/08 07:07
- 名前: 毛筒代 (ID: v/SyGyp.)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
雨とは、雲(>>5)の中の水滴や氷の粒が大きくなって落下する現象である。
[メカニズム]
雲は、雲つぶ(水滴)や氷晶(氷の結晶)によって出来ている。
海(>>120)や地面から蒸発した水分が、上昇気流に乗って温度の低い場所まで辿り着くと、雲つぶが出来る。雲つぶは上空に向かうほど大きく・重くなっていき、それが上昇気流で耐えられなくなると落下する。雲つぶは、周りの水滴とくっついて雨滴を作るが、落下する途中でちぎれてしまい、それが雨となる。
地上付近の温度が0度以下になると雪(>>9)になる。
[種類]
熱帯地域では暖かい雨、温帯地域(日本(>>14)など)では冷たい雨になる。
[[詳しい種類]]
※この節は、雨の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
※信憑性が少ないです。一部は曖昧な箇所があるので加筆・訂正してください。
・春(>>198)の雨
・花時雨
・春雨
・春の長雨
・春霖
・桜雨
・春夕立
・リラの雨
・夏(>>197)の雨
・青葉雨
・五月雨
・紫陽花の雨
・卯の花腐し
・栗花落
・半夏雨
・涼雨
・秋(>>200)の雨
・盆の雨
・秋の長雨
・秋霖
・秋出水
・秋時雨
・冷雨
・冬(>>199)の雨
・時雨
・山茶花ちらし
・風花
・冬至雨
・富正月
・寒雨
 家 ( No.2 )
家 ( No.2 )- 日時: 2025/06/08 07:07
- 名前: 毛筒代 (ID: v/SyGyp.)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※この記事は、まだ書きかけです。文章を加筆してくださる方を求めています。
家とは、
1.人(>>3)が住むための建物。
2.自分の住んでいる建物。
3.夫婦・親子・兄弟など血縁の近いものが生活を共にする小集団。
4.祖先から代々続いてきた血族としてのまとまり。
5.家族集団の置かれている社会的地位。または特に、よい家柄。
6.民法旧規定における家制度で、戸主の統轄のもとに、戸籍上一家をなしている親族の団体。
7.妻。
8. 出家に対して、在家。在俗。
のことを指す。
[概要]
※この節は中立的な観点に基づいていません。
※この節の文章は個人的な主張に基づいており、家の定義とされる記述はされていません。
家は長期的に家族が安心できなければならないとされる。家は、人々の生活や幸福にも大きく関わる。
[基本]
※この節は、家の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
家の基本としては以下が揃っていることが望ましい。
・安全と安心の提供
・心の拠り所
・自己実現の場
・健康的な生活の基盤
[時代]
※非常に短い内容の節は望ましくありません。
家は時代によって変わってきている。
 人 ( No.3 )
人 ( No.3 )- 日時: 2025/06/07 18:51
- 名前: 毛筒代 (ID: v/SyGyp.)
※記述が間違っているか曖昧です。重要な箇所は加筆・訂正してください。
※文章の短い記事は削除されやすいです。なるべく加筆・訂正してください。
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
人とは、時代において変化し続ける動物(>>4)である。
 動物 ( No.4 )
動物 ( No.4 )- 日時: 2025/06/08 06:39
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
動物とは、
1.生物を二大別したときに、植物(>>645)に対する一群。
2.人(>>3)類以外の動物。
のことを指す。
[概要]
動物は、真核・多細胞(>>27)であり、細胞壁をもたず、他の生物を食べてエネルギーを得る。
動物は、カンブリア爆発によって生まれたとされている。
これにより、
・組織の獲得
・放射相称および左右相称の体制の獲得
・前口動物と後口動物の分岐
を手に入れられた。
[界]
※この節の加筆・修正を求めています。
高校(>>64)・大学の教科書では、動物は界とされている場合が多いが、実際はそうではない。
[系統]
※一部に疑問が持たれています。
海綿動物、刺胞動物、有櫛動物が二胚葉性、その他が三胚葉性かつ左右相称動物。組織の有無という表現はない。
前口動物が、大きく脱皮動物と冠輪動物に分かれている。
多細胞動物に対してなのは襟鞭毛虫で、これはその他の系統樹でも同様である。襟鞭毛虫と後生動物を合わせた群が単系統であり、これらを合わせてコアノゾアという。海綿動物の襟細胞が襟鞭毛虫に似ていることは、1841年にすでに報告があるようである。
[分類]
※この節は、動物の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
ここでは、動物の分類について述べる。
・カイメン動物門
・平板動物門
・腔腸動物門
・有櫛動物門
・扁形動物門
・鰓曳動物門
・環形動物門
・節足動物門
・軟体動物門
・棘皮動物門
・脊索動物門
 雲 ( No.5 )
雲 ( No.5 )- 日時: 2025/06/08 07:00
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
雲とは、大気中に浮かんでいる細かい水滴や氷の粒の集まりのことを指す。
[概要]
※空白の多く概念のまとまっていない内容は好ましくありません。節を追加して、正しく述べてください。
水蒸気を含む空気が冷やされ、空気中の水蒸気がチリに付着して小さい水滴になることで雲は発生する。
誤解している人が多いが、目に見えることの出来る雲は水蒸気(気体)ではなく水(液体)である。
雲は時間によって形を変えたり動いたりする。
雲は、中学校(>>63)理科(>>561)の単元で習う。
[種類]
※この節には、雲の種類の説明がされていますが、文章が短いです。加筆・修正してください。
雲には、主に以下の種類がある。
読み方の間違えやすい雲には、()を付けている。
・層雲
広がって平らな形状を持つ雲。
・積雲
白くてふわふわとした形状を持つ雲。
・積乱雲
積雲が発達して垂れ下がった形状を持つ雲。
・雷雲
雷(>>10)を伴う積乱雲。
・雨雲(あまぐも)
水滴や氷の結晶が豊富に含まれる雲。
・雪雲
主に氷の結晶からなる雲で、雪(>>9)を降らす雲。
・霧
地表近くに広がる濃い水滴の集まり。
・乱層雲
空の低い所にできる分厚い雲。
・層積雲
空の低い所にできる雲。
・高層雲
空の中くらいの高さにでき、空全体を覆いつくすほど広範囲に広がる雲。
・巻積雲
空の高い位置にでき、氷の粒で出来た雲。
・巻層雲
空に薄く広がる雲。
・巻雲
箒で掃いた後や羽毛のような形をした雲。
・彩雲
シャボン玉のような色をした雲。
 晴れ ( No.6 )
晴れ ( No.6 )- 日時: 2025/06/08 07:18
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※この記事は、まだ書きかけです。文章を加筆してくださる方を求めています。
晴れとは、
1.空(>>8)の晴れること。
2.表立って晴れやかなこと。
3.疑いが消えること。
4. 晴れ着。
のことを指す。
[概要]
※文章のない節は望ましくありません。加筆・修正してください。
 曇り ( No.7 )
曇り ( No.7 )- 日時: 2025/06/08 07:14
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※節を追加してください。
※この記事は、まだ書きかけです。文章を加筆してくださる方を求めています。
曇りとは、
1.雲(>>5)で空(>>1)が覆われている状態。
2. 透明なものや光(>>249)をよく反射するものなどが、曇ってぼんやりすること。
3.気持ち、また表情などが、明るさを失って沈むこと。
4.公明でないこと。
のことを指す。
 空 ( No.8 )
空 ( No.8 )- 日時: 2025/06/08 07:18
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※節を追加してください。
※この記事は、まだ書きかけです。文章を加筆してくださる方を求めています。
空とは、
1.頭上はるかに高く広がる空間。
2.晴(>>6)雨(>>1)などの、天空のようす。
3.その人の居住地や本拠地から遠く離れている場所。
4.心の状態。
5.すっかり覚え込んでいて、書いたものなどを見ないで済むこと。
5.家(>>2)の屋根や天井裏、木(>>49)の梢など、高いものの上部。
のことを指す。
 雪 ( No.9 )
雪 ( No.9 )- 日時: 2025/06/08 07:33
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※過剰な文章になっています。一部は読みにくい可能性があります。
雪とは、雲(>>5)の中なかで氷のつぶが結晶になって落ちる現象である。
[概要]
※空白の多く概念のまとまっていない内容は好ましくありません。節を追加して、正しく述べてください。
通常、水(>>319)は0℃で凍るが、雲の中では0℃より低い気温の中でも水の状態で雲粒が存在している。このような水滴を「過冷却雲粒」と呼ぶ。過冷却雲粒は、-20℃の雲の中でも観測される。
雪を確認すれば、気温や湿度を確認することも出来る。
雪は、農業や水資源にも影響を与える重要な要素でもある。
[分類]
雪は、大きく分けて積雪と降雪の2種類に分類される。
積雪とは積もった雪を指し、積雪の深さを積雪深と呼ぶ。積雪深の測定は特定の時間に行われ、地面から雪面までの高さをレーザー光など使用して測る。
一方、降雪とは降っている雪のことを指す。天気(>>242)予報などで耳にする降雪量は、ある一定の時間で降り積もった雪の深さを指す。
雪には、気温が低いほど結晶が大きく乾燥しやすくなり、気温が高いほど結晶が小さく水分量が多くなるという性質がある。この性質によって、雪は様々な状態に姿を変え、それぞれの状態を示す名前で分類されている。
[[積雪]]
※この節には、雪の種類の説明がされていますが、文章が短いです。加筆・修正してください。
ここでは、積雪の分類について述べる。
・新雪
積もったばかりの雪。
・こしまり雪
新雪が積もって2~3日経過したあとの雪。
・しまり雪
こしまり雪の上に更に雪が降り積もり、その重みによって硬くなった雪。
・ざらめ雪
日中の気温で溶けた新雪。
[[降雪]]
※この節には、雪の種類の説明がされていますが、文章が短いです。加筆・修正してください。
ここでは、降雪の分類について述べる。
・玉雪
玉の形をした丸い形状の雪。
・粉雪
乾燥した細かい状態の雪。
・灰雪
灰のように舞いながら降る雪。
・綿雪
ちぎった綿のように大きくふんわりとした雪。
・餅雪
溶けかけていて、餅のように柔らかい状態の雪。
・ぼた雪(ぼたん雪)
餅雪よりも水分を多く含んでおり、雪片が比較的大きく、重たい雪。
・水雪
ぼた雪よりも更に水分量が多い雪。
 雷 ( No.10 )
雷 ( No.10 )- 日時: 2025/06/08 08:08
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※本文は分かりやすく説明してください。
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※過剰な文章になっています。一部は読みにくい可能性があります。
雷とは、
1.湿った空気が上空にのぼり、雲(>>5)が発生する。
2.雲の中で氷の粒がたくさん発生する。
3.氷の粒がぶつかり静電気が発生する。
が重なった現象を指す。
[概要]
雷が落ちることを落雷と呼ぶ。
また、雲の上部にかけて雷が移動することを雲放電と呼ぶ。
1回の雷が持つ電気(>>248)エネルギーは莫大で、電圧にすると約1億ボルトといわれている。私たちが家庭で使う電気の電圧は約100ボルトなので、この100万倍に相当する。落雷によって大きな被害が発生するのも頷けるほどの威力だといえる。
[雷鳴]
雷が落ちると、ゴロゴロという低く大きな音(雷鳴)が発生する。
この音(>>251)は、雷の通り道である空気が突然熱せられ、膨張することによって発生するものである。本来、空気は電気を通さない性質を持っているが、雷の持つエネルギーがあまりにも巨大なため、空気を引き裂いて地面に到達しようとする。このときに発せられるのが雷鳴である。
雷が通るときに周りの空気がどれくらい熱くなるのかというと、一瞬で約30000℃にまで達するとされている。これは、約6000℃とされる太陽(>>131)の表面よりも約5倍も高温なのである。
[種類]
※この節には、雷の種類の説明がされていますが、文章が短いです。加筆・修正してください。
雷には以下の種類が存在している。
・熱雷
上昇気流によって出来た積乱雲による雷。
・界雷
季節の変わり目によく発生する雷。
・渦雷
台風(>>11)など発達した低気圧の中心付近で発生する雷。
・火山雷
火山の噴火によって生じる上昇気流による雷。
・冬季雷
冬(>>199)に発生する雷。
[対策]
雷は高い所や、周囲に何もない所(グラウンド、ゴルフ場、野外プールなど)に落ちやすい。
対策としては、雷の予兆が現れたら、すぐに建物や車(>>76)の中に隠れることが望ましい。傘をさしている場合は、屈むなどして傘の先をなるべく低くすることも望ましい。
建物や乗り物の中は、電気が壁を通して地面に吸収されるため安全ではあるものの、電気器具や金属から感電する可能性もある(場合によっては電気器具が壊れることも)。感電リスクを避けるため、電気器具、天井、壁などから1m以上離れると、よりよい。
また、気象庁のナウキャストでは、雨(>>1)雲や雷雲、竜巻などの発生状況を発信している。
[雷をもたらす雲]
※文章の短い節は好ましくありません。加筆・訂正してください。
雷をもたらす雲は、雷雲・積乱雲・入道雲である。
[距離]
※独自研究の恐れがあります。
一瞬だけ光る雷は、雷が光ってから雷鳴までの時間で、おおよその距離を表せる。
音速は、時速340m/sとされているので、雷が光ってから雷鳴までの時間が5秒間だとすれば、340×5として大体1700m(1.7km)周辺で雷が発生したと考えられる。
[雷サージ]
※文章の短い節は好ましくありません。加筆・訂正してください。
電子機器等を破壊するほどの威力を持つ過電圧を雷サージと呼ぶ。
 台風 ( No.11 )
台風 ( No.11 )- 日時: 2025/06/08 13:09
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※非常に雑多な文が含まれており、一部の人は読みにくいかもしれません。
台風とは、熱帯の海上で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼び、このうち北西太平洋(赤道(>>885)より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを指す。
[概要]
台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋(>>413)高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風(偏西風)により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動く。また、台風は地球(>>128)の自転の影響で北~北西へ向かう性質を持っている。
台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲(>>5)粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達させる。しかし、移動する際に海(>>120)面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2~3日で消滅してしまう。また、日本(>>14)付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って温帯低気に変わる。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて熱帯低気圧に変わることもある。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからである。
[名称]
台風は、場所によって名称が変わる。
・台風
北西太平洋または南シナ海。
・ハリケーン
北東大西洋(>>414)、北大西洋、メキシコ湾、カリブ海。
・サイクロン
北インド(>>415)洋(アラビア海、ベンガル湾)。
また、最大風速の定義にも若干の違いがあり、ハリケーンは約33m/s以上、サイクロンは台風と同じく約17m/s以上とされている。
[大きさ]
台風の大きさは、強風域(風速15m/s以上)の広さによって決定される。経路図では通常、黄色い円で表示される。
・大型
強風域の半径が500km以上800km未満。
・超大型
強風域の半径が800km以上。
[強さ]
台風の強さは、最大風速によって段階に分類される。
・強い
33m/s以上44m/s未満。
・非常に強い
44m/s以上54m/s未満。
・猛烈な
54m/s以上。
また、台風情報では「大型で強い台風」、「超大型で非常に強い台風」などと表現される。
[単位と階級分け]
台風の中心気圧を表す単位にはヘクトパスカル(hPa)が使用されている。この数値が低いほど強い低気圧となり、強風になる可能性が高くなる。
1951年以降、日本へ上陸直前の台風で最も低い中心気圧は925hPaだった。
[仕組み]
台風の誕生は、熱帯の海上で始まる。水温が27度以上の海域で、大気の状態が不安定になると、積乱雲が発生する。これらの積乱雲が集まり、組織化されると熱帯低気圧となる。
[進路]
※この節には、節名と関係のない内容が記載されています。節名と関係のない内容は削除するか、別節を作成するか別節に移動させてください。
台風の進路は季節によって変わる。
台風の発生には、海面からの水蒸気の供給が不可欠である。暖かい海面から蒸発した水蒸気が上昇気流となり、凝結する際に放出される潜熱が台風のエネルギー源となる。このプロセスが継続することで、台風は勢力を増していく。
台風の進路は、大気の流れに大きく影響される。一般的に台風は西よりに進み、その後、北に向きを変えて日本付近に接近する。この動きには、地球の自転による影響(コリオリの力)が関係している。
春先には台風の発生緯度が低く、フィリピンなど西側の進路を通ることが多くなる。一方、夏になると、より高緯度で発生する台風が増え、太平洋高気圧の周りをなぞるような進路で日本付近へと北上してくる傾向がある。
台風の発生数は8月が最も多く記録される。しかし、8月に発生した台風は経路が不安定な事が多く、日本に接近する台風が増えるのは通常、9月以降である。
[台風の目]
コリオリの力により、北半球では台風は反時計回りに回転する。この回転は台風の構造を維持し、さらなる発達を促す。
台風の中心付近では強い上昇気流が発生し、周囲から空気が吸い込まれる。この上昇気流が台風の目を形成する。
[命名の仕方]
アジア太平洋地域の国々が協力して、台風にアジア名を付けることで、防災意識の向上を図っている。例えば2024年の最大の台風は第10号で、アジア名は「サンサン」だった。
[気象測器]
最新の研究では、台風の観測技術が飛躍的に向上している(いつ?)。
例えば名古屋大学の研究グループは、航空機から投下する気象測器を開発し、台風の目の中の詳細なデータを取得することに成功した。これにより、台風の構造や強度変化のメカニズムがより深く理解されつつあるとされている(誰によって?)。
[災害]
※この節は、台風の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
台風は、以下の災害をもたらすことが多い。
・土砂災害
・洪水
・暴風(>>272)
・高波(>>684)
[[二次災害]]
また、以下の二次災害をもたらすことも多い。
・飛散物による怪我(>>463)
・大量の廃棄物
・土砂災害
・洪水・浸水
・停電・断水
・交通の遮断
[[高波]]
日本では、以下に高波が起こりやすい。
・東京湾
・伊勢湾
・大阪湾
・瀬戸内海
・有明海
[対策]
※非常に短い文章の節は削除される可能性があります。修正・訂正してください。
台風の対策として、キキクルがある。
[風]
台風の風には、以下の呼び名がある。
・アイウォール
台風の眼を囲うようにある背の高い雲。非常に発達した積乱雲で形成されており、その下では猛烈な暴風雨(>>1)となっている。
・スパイラルバンド
アイウォールの外側の雨雲。その下では激しい雨が連続的に降る。
・アウターバンド
スパイラルバンドの外側で約200~600㎞にわたって存在する雨雲。断続的に激しい雨や雷(>>10)雨があり、時には竜巻が発生することもある。
 地震 ( No.12 )
地震 ( No.12 )- 日時: 2025/06/08 13:35
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※出典を用いていないか不十分です。出典が無いと信頼できる情報源も無くなり、削除される恐れがあります。
※非常に雑多な文が含まれており、一部の人は読みにくいかもしれません。
地震とは、地球(>>128)の地下にあるプレート(地殻)がずれ動く現象である。
[概要]
プレートとは地球の表面を覆う、10数枚の厚さはおおよそ100kmほどからなるといわれている岩板である。
また、震度は揺れの大きさ、マグニチュードは規模の大きさである。
[震度]
震度は、1から7まで存在している。
・震度0
人が揺れを感じないレベル。
・震度1
建物の中にいると微かな揺れを感じる人もいるが、ほぼ感じないレベル。
・震度2
建物の中にいると多くの人(>>3)が揺れを感じるレベル、電灯・カーテンなどが微かに揺れる。
・震度3
建物の中にいるとほとんどの人が揺れを感じるレベル、恐怖感を覚える人もいる。
・震度4
吊っているものが大きく揺れ、置物が倒れる場合もある。一部の人が身を守ろうとする。
・震度5弱
置物は倒れ、窓ガラスが割れることもある。ほとんどの人が身を守ろうとする。
・震度5強
恐怖感を非常に強く感じるレベル。ブラウン管テレビ(>>23)がテレビ台から落ちるほどの揺れ。
・震度6弱
一部の建物の壁が割れ、古い木造建物なら倒壊する恐れもあるレベル。立っていることが困難。地割れや山崩れする場合もある。
・震度6強
ほとんどの建物の壁が割れ、鉄筋コンクリートの建物が倒壊する恐れもあるレベル。立っていることすらできない。
・震度7
耐震性の高い建物も倒壊の恐れがあるレベル。大きな地割れや山崩れが発生し、地形が変形、揺れで自分の意思では行動できなくなるレベル。
[原因]
※この節は、地震の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
地震の原因としては、以下の2つが考えられている。
・プレート自体が動く説
・マントルが動く説
[プレート]
※この節は、地震の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
プレートの種類は以下のとおりである。
・ユーラシアプレート
・北アメリカ(>>15)プレート
・南アメリカプレート
・太平洋(>>413)プレート
・ココスプレート
・ナスカプレート
・カリブプレート
・アフリカプレート
・南極(>>404)プレート
・アラビアプレート
・インド(>>415)・オーストラリア(>>510)プレート
・フィリピン海プレート
[被害]
※ここでは、地震の被害ではなく東日本大震災の被害について述べています。加筆・訂正してくださる方を求めています。
実際に日本(>>14)で起こった過去最大の地震は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災(>>721))である。
明治時代(>>700)より過去の地震は、地震を観測できる体制が整っていなかったため、それ以降の事例となる。
この地震は、太平洋三陸沖で過去最大のマグニチュード9を観測した地震である。
日本政府が決定した名称は、東日本大震災である。
具体的には、余震も含めると死者はおよそ15000人、建造物もおよそ400000戸が破壊された。
震源の域も、約10万平方キロの広範囲にわたった。
この直接的な被害額も少なくとも16兆円にのぼると推測されている。
・スコシアプレート
・ファンデフカプレート
[これから起こる地震]
※この節の内容は、100%の正確性を求められる文章ではありません。
※この節には、地震の種類の説明がされていますが、文章が短いです。加筆・修正してください。
ここでは、これから起こる地震について述べる(一部は、地域により名称が変わることもあるので注意)。
・南海トラフ地震
日本の太平洋側に沿って起こると予測されている巨大な地震。
・首都直下地震
東京都(>>275)を中心とした地域で起こると予測されている地震。
・東海地震
静岡県(>>321)や愛知県(>>297)などを中心とした地域で起こると予測されている地震。
[対策]
地震の対策としては、7つの備えがある。それは以下のとおりである。
・自助、共助
自分でできること、家族でできること、ご近所と力を合わせてできること、などについて考える。
・地域の危険を知る
防災マップ(ハザードマップ)を見て、自然災害が発生した場合の被害予測や避難・救援活動に必要な情報を確認する。
・地震に強い家(>>2)
法律で定められた耐震基準を満たした、丈夫な家に住む。
・家具の固定
大きな家具や電化製品が倒れないように固定する。
・日ごろからの備え
外出するとき、職場・学校にいるときなど、場所に合わせた非常時への備えをしておく。
・家族で防災会議
家族が揃っていないときに災害が発生したとき、どうするかを話し合う。
・地域とのつながり
大災害の時は近所の人同士の助け合いが大切。普段から近所の人に気を配ったり、防災訓練に参加したりする。
[地震情報]
※この節は、地震の種類を雑多に並べただけです。文章は雑多に並べず、説明などを用いて分かりやすくしてください。
地震が起こると、メディア等により以下の情報が到達される。
・緊急地震速報
・震度速報
・震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報
 梅雨 ( No.13 )
梅雨 ( No.13 )- 日時: 2025/06/08 15:46
- 名前: ヨモツカミ (ID: xwCD.5ek)
※この記事は、良質な記事として選ばれています。詳しくは>>0の[良質な記事]を参照してください。
梅雨とは、6月から7月ごろにかけて、雨(>>8)の日が続く現象である。東アジアの一部地域でみられる現象である。[1]
[概要]
日本(>>14)では、沖縄県(>>446)から東北地方まで広い範囲が梅雨の影響を受けるが、北海道(>>129)には梅雨がないと言われている。[1]
しかし、北海道では必ず梅雨の影響を受けないという訳でもなく、影響自体は少ないが蝦夷梅雨と呼ばれる時期も存在する。
[梅雨入りと梅雨明け]
梅雨に入ることを梅雨入り、梅雨が明けることを梅雨明けという。[2][3]
梅雨入りと梅雨明けは、地域によって異なる。[3]
[由来]
梅雨の由来は、もともと中国(>>17)発祥である。ただ、なぜ梅雨という呼び名になったのかは、様々な諸説がある。[3]
[原因]
梅雨の原因は、以下のとおりである。[1]
・梅雨前線による影響
梅雨になると、梅雨前線が出来る。これは、南から来る暖かく湿った空気と、北から来る冷たく乾いた空気がぶつかってできる線である。
・太平洋(>>413)から湿った空気が流れこむ影響
太平洋高気圧が大きくなると、南から湿った空気をどんどん日本に送りこむ。この湿った空気が山や前線にぶつかって上昇し、雲(>>5)になって雨を降らせる。
・偏西風による影響
上空を西から東に吹く強い風を偏西風と呼ぶ。
この風が強いと梅雨前線が北に押し上げられて梅雨が明けやすくなるが、逆に弱まると前線が停滞して雨が長引く。
[特徴]
梅雨の特徴は、以下のとおりである。[1]
・雨の日が続く(シトシト降ることもあれば、大雨も)
・湿気が多く、ジメジメする
・気温は高すぎず、ムシムシと感じることが多い
・晴れ(>>6)る日が少なく、日照時間が短くなる
[農作物]
梅雨の時期は、ストレスなどのデメリットが多い中で、以下のようなメリットもある。[1]
・植物(>>645)がぐんぐん育つ(田んぼや森(>>715)も)
・ダムや川(>>121)の水(>>319)をたくわえて、夏(>>197)の水不足を防ぐ
・農作物が元気に育つのに必要な恵み
[対策]
梅雨の時期は、気温・湿度・気圧の変化によって、体調不良・カビ・食中毒などのトラブルが起こりやすくなる。[2]
梅雨の対策としては、規則正しい生活習慣や食事、適度な運動や水分補給、換気や除湿などを心がけることが大切である。[2]
[出典]
1.https://yurukizi.com/tsuyu-wakaru/
2.https://kiset-season.com/archives/14679
3.https://domani.shogakukan.co.jp/526027
 日本 ( No.14 )
日本 ( No.14 )- 日時: 2025/06/08 16:27
- 名前: 毛筒代 (ID: xwCD.5ek)
※節に関係のない文章が入れられています。節を追加してください。
※独自研究が含まれている可能性があります。加筆・訂正してください。
※この記事は、中立的な観点に基づいていません。必要のない箇所は訂正してください。
※出典は列挙するだけでなく、どの文章を用いているかを正しく述べてください。
日本とは、東アジア地域に位置する、南は太平洋(>>413)、北は日本海に囲まれた島国である。[1]極東の国とも呼ばれる。[2]
[概要]
日本の首都は東京である。[1]
日本は地域を8区分に区切られており、北海道(>>129)地方、東北地方、関東地方、中部地方を東日本、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方を西日本と呼ぶ。[1]
日本は、北は北海道から南は沖縄県(>>446)まで全部で47都道府県で構成される国である。47都道府県からは更にその中で市区町村と分かれている。[1]
[GDP]
日本のGDPは、約4.73兆ドル(約500兆円)である。
[自然]
日本は自然が多く、世界有数の森林大国である。また、国土の約7割が森林と言われている。[1]
日本には、全土に渡り複数の山地や山脈が存在し、特に山地の割合が高い国である。[1]
日本を縦断するように山地や山脈があるため、日本海側では雪が多いことも特徴である。[1]
日本の山々では富士山が有名で、その高さは日本一高い3776メートルである。[1]
また、日本は春(>>198)夏(>>197)秋(>>200)冬(>>199)という四季がある。[1]
[人口と言語]
日本の人口は約1億2700万人である。東京都(>>275)には約900万人の人口がいる。[1]
都道府県で人口にばらつきがあり東京は一番人が多く住んでいるが、過疎化している地域もある。[1]
日本は少子高齢化(>>797)で、全国民の約30%が65才以上である。同時に、日本は長寿の国と言われ平均寿命は84歳、男性は81歳、女性は87歳である。[1]
海外に住む日本人は約130万人、日系人は400万人以上である。[1]
言語は日本語が共通言語で、ひらがな、漢字、カタカナの3種類で表される。[1]
地域によって特有の単語やイントネーションがあり、それを方言という。一般的には関東地方、特に東京都で話される言葉が標準語とされている。[1]
最近では、外国の言葉に翻訳されることなく日本語がそのまま有名になっている言葉もある(kawaiiなど)。[1]
[宗教]
日本は無宗教の人(>>3)が多い。[1]
割合的には、仏教や神道を信仰している人が多い。[1]
[文化]
日本の文化で海外でも有名なものはマンガ(>>20)、アニメ(>>29)である。[1]
アニメにおいては、各国でもジブリやドラえもん(>>490)などがテレビ(>>23)などで放送されている。[1]
日本の伝統衣装は着物である。[1]
また他にも空手(>>637)や柔道(>>635)などの武道、茶道(>>574)や書道など、~道とつく文化も日本特有である。[1]
文化の一つとして、日本食も世界に知られている。[1]
和食は、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されて、より世界で注目を浴びるようになった。[1]
[出典]
1.https://column.aiai-navi.com/blogs/view/4
2.https://sekaika.org/japan-ol/
3.https://studyinjpn.com/ja/column/about_japan
 アメリカ ( No.15 )
アメリカ ( No.15 )- 日時: 2025/06/10 17:19
- 名前: 毛筒代 (ID: KhbtCCuk)
※この記事は、良質な記事として選ばれています。詳しくは>>0の[良質な記事]を参照してください。
※この記事には、必要な情報が不足しています。詳しくは[出典]から必要な情報を書き抜いてください。
※一部は小説カキコにより反映できない為、スペルミスがあります。
アメリカ合衆国(略:アメリカ)とは、北アメリカ大陸に位置する国で、世界で最も影響力のある国でもある。[2]
本記事では、アメリカと略する。
[概要]
ここでは、アメリカの主な情報について述べる。[1]
アメリカの人口は、334914895人である(2023年時点)。
また、国土面積は9833517平方キロメートルとなっており、人種は、白人が58.4%、黒人が13.7%、アジア系が6.4%、ヒスパニックが19.5%、その他が2.0%となっている(2024年時点)。
宗教は、キリスト教が70.6%、ユダヤ教が1.9%、イスラム教が0.9%、仏教が0.7%、無宗教が22.8%となっている(2014年時点)。
首都はワシントンD.C.であり、時差は日本(>>14)と比べて-14時間から-19時間(サマータイム時は-13時間から-19時間)ある。
公用語は、主に英語(>>16)が使われており、レートは1USDあたり155.25円である(2024年11月25日時点)。電源は、日本と同じくAタイプである。
[人口増加]
アメリカでは、人口が増加している傾向にある。それは、多くの移民を受け入れている為である。[1]
移民の代表的な出身国はメキシコ、中国(>>17)、インド(>>415)、フィリピンであり、特にアメリカと陸続きのメキシコ系移民は、全移民人口の25%を占めている。[1]
アメリカ全体で50の州がある。[2]
また、7月4日はアメリカの独立記念日である。[3]
[歴史]
アメリカはイギリス(>>533)系移民によって作られた国である。[1]
元々はアメリカインディアンが暮らしていた土地に、15世紀末からヨーロッパから人が移り住み、イギリスの植民地が形成した。
1776年に独立宣言を発表して以降は独立国家となり、20世紀以降は世界経済を牽引するようになった。
[出典]
1.https://schoolwith.me/countries/US/basic_information
2.https://world-guide.jp/countries/840
3.https://mofa.go.jp/mofaj/area/usa/data.
全レスもどる
総合掲示板
小説投稿掲示板
イラスト投稿掲示板
過去ログ倉庫
その他掲示板
スポンサード リンク

